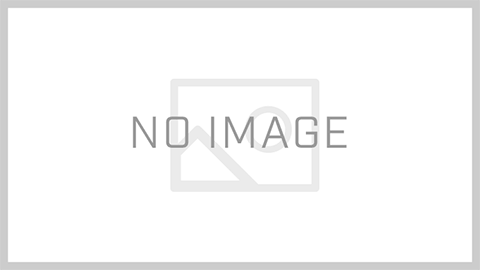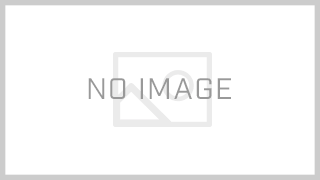“緊張のほぐし方”で検索すると、交感神経がどう、とか身体の緊張をほぐしましょう、というようなことが書かれていて、深呼吸だとか、手に「人」と書いて飲み込むとか、オカルトちっくなものも含めてその通りの実践をしても実際に効果感じられなくないか?と思うことがあったので、それだったらお父さん式の緊張のほぐし方のほうがいいんじゃないかと思ってこの記事を書きます。
まぁ、この手の手法は失敗してもデメリットはないので、一度試してみて効くようだったら採用してもらえたら嬉しいなーと思います。
効果てきめんな緊張のほぐし方
とりあえずやってみて
とりあえずの一例として書くと、
「目についたものの色を”全力の早さで”認識していく。」というもの。
周りの人の服の色、飲み物の色、カーテンの色、カベの色。目につく物は無数にあるはずなので、それらの色を「青!」「ピンク!」と全力で心の中で叫んでみる、というかんじ。
「全力でやったけど下手くそで、物を探すだけでも時間がかかっちゃう」という人でも大丈夫。その行動をすること自体に意味があるので。とにかく頭の回転を早くすることが目的です。
30秒くらいやってみて…どうかな?まだ緊張の嫌な感じする?多分とけてるんじゃないかなぁ。もし効果があると感じられたら、今後もやってみてねー。あ、他の人にその方法だれから聞いたの?って聞かれたら「こちゃって人が言ってたんだけど…」って名前を広めてもらえたら喜びます。
さて、上では”一例として”と書いた通り、緊張のほぐし方の具体的なやり方は何通りもあります。先に書いた通り「頭の回転を早くする」ことが目的なので、例えば「スマホの電話帳の上から順番に名前と顔を思い浮かべていく」でもいいだろうし、カレンダーを見ながら「何月何日は何曜日!?」と探していくとかでもおもしろいかもしれないね。
ただし、例えば「数字の2を倍々にしていく」とか、毎回同じ内容になってしまうようなものは、避けた方がいいかなーと思ってます。何故かというと、同じ内容が繰り返されると”慣れ”が出てきちゃうから。そうすると脳への負荷が減ってしまって効果が薄くなってしまうので、流動的な内容がいいんじゃないかなーと思います。
命名!「クロックアップ法」!
この”頭の回転を強制的に早くする”方法を「クロックアップ法」と自分で名づけました。このクロックアップという言葉は、パソコンのクロック、及びクロックアップという方法、考え方から来てます。個人的にこのクロックアップというのは実生活のいろんな場面で役に立つと思っていて、別の機会に詳細を書いていけたらなーと思っています。
緊張を知ろう
みんながほぐしたいのは緊張じゃない。
さて、この「クロックアップ法」ですが、厳密には緊張をほぐす方法ではありません。結論から言うと「緊張感をほぐす」方法です。どーゆーことかというと、「緊張」というものに対して緊張そのものが悪いことだ!と勘違いしている人がいるので、冒頭ではあえて緊張と書きましたが実際には違うものだということを解説したいと思います。
自身に問いかけてみてほしいのですが、緊張について考えるとき、「身体がいつもと違う感覚で、思うように動かせない感覚がする。この感覚が嫌で解消したい」ってことじゃないですか?つまり、緊張そのものじゃなくて“緊張のときの嫌な感覚”を解消したい。というのが本当の目的なんじゃないかと思う。
だって、実際よその記事でも「緊張は、とっさのことにも対応できるように体が準備している状態」と書かれていたりするでしょ?つまり、“緊張”自体は身体のパフォーマンスを上げた状態のことを指します。つまり、いい状態。だけど、実際に緊張するとそれをほぐしたいと考えるよね?それは何故か。緊張してるときには同時に”嫌な感じ”もしてるから。クロックアップ法は、その嫌な感じを取り除く方法なのです。
緊張の”嫌な感じ”の正体
これは、あくまでお父さんの推測、感覚の言語化。学術的には「交感神経が~」とか「深呼吸で落ち着ければ~」とかのほうが正しいのかもしれないけど、実態とか効果とかの面ではお父さん自身の感覚が正しいと思っているので、それを言語化したものだというのを念頭に置いてください。
緊張の嫌な感じは、一言でいうと「脳と身体のパフォーマンスのバランスが崩れた状態」のことを指すと思います。
どーゆーことかというと、例えば普段は身体のパフォーマンスが100、脳のパフォーマンスも100だったとすると、脳が身体を思い通りに動かせる割合い(便宜的に稼働率と呼ぶね)は100%だよね。
じゃあ次に、身体が緊張でパフォーマンスが一時的に120、脳は普段通り100だった場合はどうだろう?稼働率は100÷120で、約83%ほどとなる。普段より「17%近く、脳が身体を思い通りに扱いきれない感覚や不安」が、嫌な感じとして表れてしまうんじゃないかと思う。
次に、こんなケースもある。身体は普段どおりだが、脳のパフォーマンスだけがあがってしまう場合だ。身体が100、脳が120の場合、脳の要求に対して身体が83%ほどしか応えることしかできない。このパターンの不安もあると思う。
どちらのパターンも、脳と身体のアンバランスから不安が発生している。これを解消するのが、先のクロックアップ法ってこと。
何故「クロックアップ法」が効果があるのか
さて、じゃあ脳と身体のバランスが崩れた状態を、クロックアップすることで何故解消できるのか解説したいと思います。
まず、体のパフォーマンスがあがっている場合。脳が身体を持て余してる状況なので、頭の回転を早くすることで身体をしっかり制御できるようにします。頭と身体のパフォーマンスが近くなれば、不安感は小さくなる、ということです。
じゃあ、脳だけがパフォーマンスが上がっている場合はどうなのか?この時の緊張は不安”感”ではなく、不安を感じているといえます。脳が身体を制御しても脳のリソースに余りがあるので、その余裕が余計なことを考えてしまっているんだと思うんです。なので、余計なことを考えるリソースを使い切るためにクロックアップ法を使います。
つまり、2種類の緊張の原因は違っても、同じ方法でそれぞれを解消できるということです。
余談:もしかして「ゾーン」って…
どうでしょう、クロックアップ法とその理屈。納得いただけたでしょうか?別に何か実験をしたとか確たるソースがあるわけではないので、お父さんが自分で提唱してるだけですが、それでもお父さんが確かに経験して、それを言語化したものなので、お父さんが異常者というわけじゃなければそれなりに意味のある内容なんじゃないかな、と思います。
さてここで唐突ですが、お父さんの考える「ゾーン」について話したいと思います。漫画なんかでも度々登場する言葉で、漫画的に言い換えると「覚醒」とかと似たような使われ方をしている、みんな大好きな言葉、現象だと思うのですが。実はアレ、間違いじゃなければお父さんも経験したことがあります。この緊張に関する記事を書いていて思い出しました。
何故かというと、緊張とゾーンの感覚は、密接な関係があったと思い出したからです。どーゆーことかというと、あくまで仮説ですが「緊張時の身体のパフォーマンスと脳のパフォーマンスが、目の前の課題に対して丁度バランスが取れた状態」のことをゾーンと呼べるのではないかと。
今回の記事では、脳の回転を目の前の課題とは関係のないもので強制的に早める方法を書きましたが、これが目の前の課題に対して自然と行われたとき、普段とは違うものが見えてくるんじゃないかと思うんですね。
このときの感覚ですが、緊張時は不安感があったのに対し、ゾーンの際は全能感があふれ出ます。
でもまぁこれ以上は長くなるんで(すでに長い?)、ゾーンについて思うことと、お父さんの実体験については、別の記事で書こうと思います。
まとめと大前提
そんなわけで、緊張(感)の解消方法を書きました。お父さんの場合は、昔やってたピアノの発表会や、仕事でのプレゼン、飛び込みでの営業等で緊張する場面はあったけど、おかげさまでその緊張感とは現在うまく付き合えてると思ってます。むしろ心地いいくらい。だけど、それらを経て一つ言えることがあります。どんなに緊張感を味方につけることができても、発揮できるのは今までの積み上げの結果だけ、ということ。例えば準備不足や練習不足のように、自身で解消できるものを解消できないまま場に臨んでも、心の焦りはなんとかなっても最良の結果にはなりにくい。なので、何事においても日々の積み重ねは忘れないようにね。
それじゃ、今回はこのへんで。またねっ!